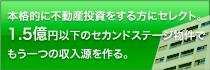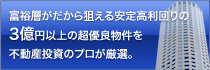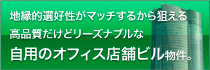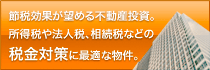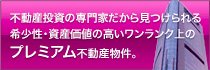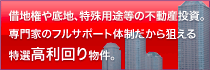レンタブル比
2009年8月11日 by Quality-F
賃貸経営は、床を賃貸する事によって生じる賃料収入が収益の源泉となる。床を賃貸すると言っても、どの部分をどう貸すのかは自由である。したがって、その賃貸される床面積(貸し方)が重要となってくる。
建物全体の中で、どれだけの部分を賃貸する事が可能であるかを示す指標(割合)として用いられるのが、一般にレンタブル比(賃貸面積/延床面積)である。
まずベースとなる延床面積(分母)について説明したい。一般に用いられるものは、建築基準法上の法延床面積や容積対象床面積、その他、施工サイドが工事費算定の際に用いる施工床面積、不動産登記法による登記床面積がある。
この中で、レンタブル比を把握するために多く用いられるのが実測(法延床面積)である。これは、建築基準法により定められた算定方法によって求積された面積である。簡易的なイメージとしては、壁で囲まれた面積との認識で良いであろう。ただし、開放性の観点からバルコニーや屋外廊下等ややこしい話はあるが、本件では割愛させていただく。次に、素人でも簡単に、また簡易的に用いられるのが登記床面積である。これは、法務局備え付けの建物不動産登記簿謄本に記載のある面積である。基本的には法延床面積の考えとほぼ同じである。公開されているため誰でも入手できることから、利用し易く、かつ、唯一のもので非常にわかり易い。
当該面積を基準とすれば、マンション等についてのレンタブル比は概ね90%程度、屋外階段や屋外廊下等の屋外部分の状況や屋内駐車場の状況などにより誤差はあるものの、大きくずれるような事はない。これは、計画にあたって、賃貸であれ、分譲であれ、有効面積(賃貸可能面積・分譲可能面積)を最大限大きくするのは、当然のことであり、結果的に一定の水準に収斂することとなる。ただし、ハイグレード物件等の特殊性を有する物件は独自の収益構造の上に成り立っている事から、一般的な水準とはかけ離れるケースもある。
また、アパート等についてはレンタブル比が100%を越えるケースも多々見受けられる。これは、登記床面積に対して賃貸面積がメーターボックスやアルコープ等の外部まで含んだ面積で計算されるためにおこる現象である。
一方、オフィスについては、必要最低限の共用部(トイレ・階段等)の影響から高い水準でも80~85%程度である。エントランスや共用部の配置によって大きく異なり、大規模なオフィスビルでは60~70%程度となっており、小規模なオフィスビルでは80%~程度である。中には自社ビルを賃貸ビルに変更したケースでは個別的な共用部分の影響でレンタブルが50%程度しかなかったケースも見受けられた。また、超高層のSクラスビルにおいては壮大な共用部面積の為、60%を切ってくるものも見受けられる。
オフィスの契約形態は多様多種である。一般に、事務所として通常使用できる部分を賃貸面積として賃貸するノーマルなケースをネット貸しと言う。また、1フロアに1テナントの場合などにはトイレ等の共用部分を含むフロア単位の面積で契約されているケースも多く、これをグロス貸しと言う。このケースは、特に小規模ビルに多く、入居テナントにとっても自分たちのみで利用でき、外部の第三者を特定しやすいという防犯の面でも役立つことから当該形態での契約を容認している。このような形態であると、グロス貸しでどこまでの範囲を賃貸するかによって変わるもののレンタブル比90%といった場合も見受けられる。外観上もEVが開いたら、いきなりテナントの部屋になっていたりするのでわかりわかりやすい。小規模のオフィスビルにとっては、貸せる可能性のある部分は全て賃貸することにより、収益の最大化を図っている。繁華性の高い都内の駅前店舗ビルなどの多くはこの形態を取っている。このように契約形態も多種多様である為、どういった契約面積で賃貸しているかを確認することは重要であり、レンタブル比率からその内容の端緒はすぐに見当はつくものである。